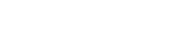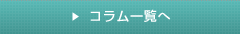大阪で交通事故の相談なら士道法律事務所
2017.09.06示談金額について
交通事故の後遺症(4)~後遺症による逸失利益 その2~
後遺症による逸失利益の計算方法は前回の記事で述べたとおりです。
逸失利益を計算するに当たって一番問題となりやすいのが「基礎収入額」の算定方法です。
「基礎収入額」を計算するに当たり、被害者の属性は概ね次のように分類されます。
(A)有職者の場合
a.給与所得者 b.事業所得者 c.会社役員
(B)家事従事者の場合
(C)無職者の場合
a.学生・生徒・幼児等 b.成年の失業者・無職者
順に計算方法を見ていきましょう。
(1)給与所得者
最も単純なケースです。
一般的な会社員等であればこれに該当し、原則として事故前の収入額が「基礎収入額」となります。
現実の収入が賃金センサス(日本の賃金の統計データ)より低い場合、事故後に昇給や転職が予定されていたといった事情があれば、賃金センサスの平均収入額が「基礎収入額」とされることもあります。
事故時に概ね30歳未満の若年労働者だった場合、将来の増収も考慮しなければなりませんので、原則として全年齢平均の賃金センサスを用いて「基礎収入額」を算定します。
(2)事業所得者
自営業者、自由業者、農林水産業者等がこれに該当します。
原則として確定申告の収入額を「基礎収入額」とします。
確定申告の額と実際の収入額が異なる場合には、それを立証すれば実収入額が「基礎収入額」となります。
収入額の変動が大きい業種である場合や開業直後に事故に遭ったような場合には、特別な統計資料を利用したり、賃金センサスの平均収入額を採用したりして「基礎収入額」を算定することもあります。
(3)会社役員
社長、専務等の役員で役員報酬を得ていた場合、基本的に休業損害や逸失利益は認められません。
それは、役員報酬というものが基本的には「会社の利益の配当」という性質を持つからです。
利益の配当なのだから、その役員が働けなくなったとしても会社から役員に対して役員報酬は支払われる。
実際の減収がないのだから、休業損害や逸失利益は生じない。
だから加害者(保険会社)が事故に遭った役員の休業損害や逸失利益を支払う必要はない。
こういう理屈が成り立ちます。
この理屈自体は法的に正しいです。
しかし、中小企業の場合、役員報酬に取締役の労務の対価としての性質を有する部分が含まれていることがあります。
例えば、役員が建築現場作業に従事していた、経営者であると同時に開発業務に携わる技術者である、高度な専門性や知識を生かして自ら顧客先に足を運んでいたというようなケースです。
このような場合には労務の対価部分(役員報酬の一部)の減収分が「基礎収入額」とされることがあります。
労務の対価部分が役員報酬の何%なのか、ということは事案ごとに異なるので、個別の検討が必要となります。
(4)家事従事者
いわゆる主婦(主夫)のことです。
専業の場合、現実の収入はありませんが、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金額を「基礎収入額」とします。
有職の場合、実収入が上記平均賃金額を上回っていれば実収入額を、下回っていれば平均賃金額を「基礎収入額」とします。
(5)学生・生徒・幼児等
未就労の学生等の場合、交通事故に遭う前の現実の収入というものはありません。
しかし、将来就労する蓋然性は高いので、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均賃金額を「基礎収入額」とします。
予備校生であっても、成績優秀で大学に進学できた蓋然性が高いといった場合には、高卒ではなく大卒の平均賃金額が「基礎収入額」とされることがあります。
また、大学院生で内定先が決まっていて、将来的に一定の地位まで昇格する蓋然性が高いといえるケースで、通常の大卒全年齢平均賃金額の1.4倍の金額が「基礎収入額」とされた事例もあります。
(6)成年の失業者・無職者
一時的な失業者でその後就労する蓋然性が高いといえる場合、再就職によって得られるであろう収入額が「基礎収入額」となります。
この「再就職によって得られるであろう収入額」というのは、特段の事情がない限り、失業前の収入額を参考にします。
生活保護受給者や無職者の場合、休業損害や逸失利益は原則として認められません。
交通事故による減収というものが観念できないからです。
ただし、事業を始めたり就労したりする意志や蓋然性があったといえる場合には、賃金センサスに基づいて一定金額が「基礎収入額」とされることがあります。
関連の記事
関連記事はまだありません。
交通事故解決には様々な知識が必要です。
このコラムでは交通事故に関しての様々な情報を公開しております。
カテゴリーCATEGORY
-
- 法律相談について
-
-
- 弁護士費用について
-
-
- 示談金額について
-
-
- 後遺障害について
-
-
- 死亡事故について
-
-
- その他
-